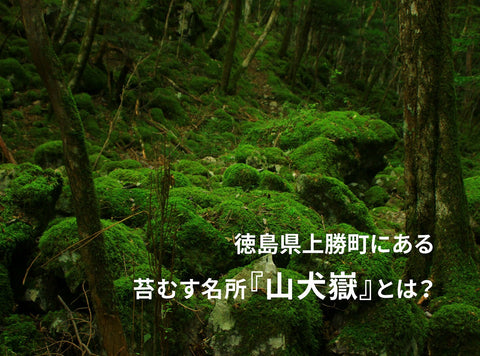上勝阿波晩茶をご存知ですか?
上勝阿波晩茶は、徳島県上勝町で作られた阿波晩茶のことです。
近年、晩茶は様々な効能が期待されることから健康茶の一つとしても注目されていますが、まだあまり馴染みがない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、今話題の「上勝阿波晩茶」について、その特徴や製法をご紹介します。
最後には、私たち RISE & WIN Brewing Co. のメンバーが上勝阿波晩茶の茶摘みに参加した際の様子もお届けします。
![]()
![]() 上勝阿波晩茶とは?
上勝阿波晩茶とは?

上勝阿波晩茶は400年を超え、徳島県上勝町でつくられている阿波晩茶のことで、長く引き継がれてきた伝統的な独自の製法によるお茶の一種です。
世界的にも珍しい乳酸発酵による後発酵茶であり、2021年には、国の重要無形民俗文化財にも指定されました。
その味わいはどこか懐かしく、口に含むとまずやわらかな酸味が広がり、爽やかな後味がすっと残ります。
緑茶のような渋みはほとんどなく、むしろ丸みのある穏やかな風味です。
一口飲むと、上勝の山里の空気や、昔ながらの暮らしの営みがふっと感じられるような、素朴で奥深さのあるお茶です。
![]()
![]() 上勝阿波晩茶の伝統的な製法
上勝阿波晩茶の伝統的な製法

現在では、人の手だけでなく機械も取り入れながら、より効率的な方法で作られることもあります。
ただし基本となる工程は変わらず、
①摘む → ②茹でる → ③擦りつぶす → ④漬けて発酵・熟成 → ⑤干す
という流れで進められています。
まず、一枚一枚手摘みされた茶葉は、窯で茹でて熱処理を行います。その後、摺り揉みを経て、桶や樽に漬け込むことで乳酸菌による発酵が始まります。茶葉は数週間かけて発酵し、最後に天日干しされます。そして、完成したものは、9月中旬以降に全国へと出荷されていきます。
上勝町では出荷用に生産されているものもありますが、もともとは庭や山で摘んだ茶葉を仕込み、家庭で飲まれていたものでした。
そのため製法へのこだわりや、茶葉が育った環境、仕込みに使う蔵や木桶に根付いた土着菌の違いによって、作り手ごとに風味が異なり、それぞれ個性豊かな味わいを楽しむことができます。
こうして仕上がった上勝阿波晩茶は、カフェインが少なく、食事と合わせても飲みやすいため、日常の中で気軽に取り入れられるのも魅力のひとつです。
また、抗アレルギー作用やオートファジーの働きが期待できるともいわれ、美容や健康の観点からも注目を集めています。
近年では、日々の暮らしに寄り添う“体にやさしいお茶”として、ますます人気が高まっています。
![]()
![]() 茶摘み体験レポート
茶摘み体験レポート

RISE & WIN Brewing Co.では、「KAMIKATZ IPA」をはじめ、上勝阿波晩茶を使ったクラフトビールをつくっています。まさに、晩茶はカミカツビールにとって欠かせない存在です。
今回は、いつもお世話になっている上勝阿波晩茶の生産者Kamikatsu-TeaMateの百野大地さんを訪ね、茶摘みの現場にご一緒させていただきました。
普段はビール造りに向き合うブルワーにとって、茶摘みは初めての体験。慣れない作業に苦戦しながらも、夢中になって茶を摘んできました。
 茶摘みの前に、まず指にテーピングを巻くよう勧められました。上勝阿波晩茶の茶葉は、春摘みの柔らかな新芽ではなく、夏に収穫される硬くてしっかりとした葉。枝元から葉だけを引くように摘むため、軍手をしていてもすぐに指を痛めてしまうのです。
茶摘みの前に、まず指にテーピングを巻くよう勧められました。上勝阿波晩茶の茶葉は、春摘みの柔らかな新芽ではなく、夏に収穫される硬くてしっかりとした葉。枝元から葉だけを引くように摘むため、軍手をしていてもすぐに指を痛めてしまうのです。
そして、収穫した茶葉を入れる腰籠をつけると、いざ茶摘みスタートです!

単純そうに見える作業も、やってみればなかなか骨が折れるものでした。それでも、茶葉がきれいにサッと枝から外れた瞬間は心地よさがありました。

何よりも、キツかったのは急こう配な斜面。足を踏ん張らないと滑り落ちてしまうどころか、お茶の木に届きません、、(泣)
慣れた手つきで摘んでいく百野さんを横目に少しずつコツを掴んでいきます。
茶摘みをしながら、百野さんから上勝阿波晩茶のことを色々と教えていただきました。
TVなどで健康茶として取り上げられ人気が高まる一方で、高齢化によって茶畑の管理や維持が難しくなっているケースが増えているといいます。
今回、お邪魔させていただいた茶畑も、高齢化などの理由により管理できなくなってしまったところ、受け継いでいるのだそうです。そもそもこのお茶は、もともと家庭用に作られていたもので、自分の家で必要な分だけを摘み取り、仕込み、消費する -いわば自家消費を前提とした自給的な営みが中心だったようです。
こうした背景もあり、上勝阿波晩茶の価値をさらに高め、生産者を増やしていく取り組みも進められているようです。また、一度荒れてしまった茶畑の再生も行っているそうですが、やはり管理できる規模にも限界があるとのことです。
私たちもカミカツビールを通じて、この上勝阿波晩茶をより多くの人に知っていただくきっかけになれれば、と改めて感じました。
 やっと茶葉が籠いっぱいに!籠をいっぱいにするのも結構時間がかかりました。
やっと茶葉が籠いっぱいに!籠をいっぱいにするのも結構時間がかかりました。
有難いことに曇り空の下で作業することができましたが、湿気がすごく、暑さもあって終始汗が止まりませんでした。普段、熱気に包まれた環境でビール仕込みをしているブルワーもさすがに、参っているようでした。
実際に体験してみると、改めて生産者の方々の苦労が身にしみて感じられました。上勝阿波晩茶は、伝統文化として大切に受け継がれてきただけでなく、茶摘みや仕込みを通じて人と人とのつながりを育む場となっているのだと思います。
上勝阿波晩茶は、まさに「暮らしと文化が息づくお茶」そのものだと感じました。
まとめ
 いかがでしたでしょうか?
いかがでしたでしょうか?
上勝阿波晩茶は、400年以上にわたり守り継がれてきた希少なお茶であり、地域の暮らしや文化を今に伝える貴重な存在です。高齢化による課題を抱えながらも、その価値を高め、次世代へとつなごうとする取り組みが広がっています。
お茶を摘み、仕込み、味わう──。
そんな日常の営みから生まれた上勝阿波晩茶は、今も人々の暮らしと文化を結びつけています。その一杯は、自然の恵みや生産者の思いを感じさせてくれます。
ぜひ皆さんも、上勝阿波晩茶を手に取り、そのやさしい味わいを通して、上勝町の文化や人々の営みに触れてみてください。
RISE & WIN Brewing Co.では、記事中でも取り上げた「KAMIKATZ IPA」などのクラフトビールに、製造過程で砕けてしまった葉や茎などの規格外品の上勝阿波晩茶を活用しています。
『 カミカツIPA 』
柑橘感のあるアメリカンホップのフルーティーな香りとドリンカブルな飲み心地が特徴のWest coast IPA。 飲みごたえのある苦味の中に、お茶のようなほんのりとした甘みも感じられる。
RISE & WIN Brewing Co.

日本ではじめてゼロ・ウェイスト宣言を行った、徳島県上勝町(※)に拠点を構えるブルワリー。
美味しいクラフトビールを仲間とカジュアルに楽しむ、ただそれだけで美しい環境を守り、社会課題を知る小さなきっかけとなる。RISE & WINはそんな心地良い循環を目指し、ビールを「ゼロ・ウェイスト活動を自分事化するための手段」と捉え、上勝の暮らしや体験に根ざした魅力を発信しています。
“JUST DRINK KAMIKATZ BEER”
美味しいビールを楽しむだけで 「環境にちょっと良いコト」に繋がっている
※上勝町は2003年よりごみの再利用・再資源化に力を入れ、現在では日本屈指のリサイクル率80%以上を実現するに至りました。